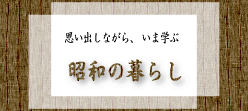|
||||||
| ■農家の子を友達にもったおかげで、ひもじい思いをせずにすみました けっして江戸時代の話ではありません。昭和20年代から30年代にかけてのことです。おやつといえば、たまに5円か10円のお小遣いをもらって、駄菓子屋へ走ることもありましたが、お金を出して買わなくても、身の回りには食べるものが十分にありました。わが家にもりっぱな畑があり、実のなる木がたくさん生えていましたが、それだけではありません。1年生から4年生まで通った地元の小学校は、8割ほどが農家でしたから、当然、友達も農家の子が多くなります。遊びに行くと、いろいろなものを食べさせてもらえました。畑になっているトマトやキュウリ。キュウリには塩をゴシゴシすり込んで食べました。ダイコンやニンジンを引っこ抜き、肥後守(小刀)で皮をむいてガリガリ食べました。ときには甘いウリやスイカまで。サトウキビを作っているところもあり、茎が太ってくると、30センチほどの長さに切り分け、腰のベルトに3本ばかり刀のように差して、遊び回りながら食べました。皮が固いですから、気をつけて食べないとケガをします。 そのころはビニールハウスなんてほとんどなく、みんな露地栽培で旬の時期にしか食べることはできません。また、肥料といえば下肥が主体ですから、いまでいう有機農法。そんなわけで、あのころの農作物の味の良さはいまでも舌に記憶されています。なんとぜいたくな食生活だったか、ふとそう思うことがあります。数年前、小学校と高校の3年先輩で、農家に育ったKさんが、地元の新聞に自伝を掲載されていましたが、その中で、こんなことを書かれています。中学生か高校生のころ、家に遊びに来た友達に、(こんなものを出してバカにされはしまいか)と思いながら、おやつにモチと納豆を出したというのです。モチ米も大豆も自分の家の田畑でとれたもの。モチも納豆も自家製。つまり100パーセント手作りのおやつです。そのときの友達がいまでも当時を思い出して、「あんときのモチと納豆はうまかったなあ」と言ってくれるそうです。Kさん自身も、あれは確かにおいしかったし、ぜいたくな食べ物だったと思うそうです。ただ、農と食が混然一体だった当時だからこそできたことで、いまでは、農家でもよほど条件が揃わないと無理だとか。 ■畑でなくても食べられるものがいっぱい ぼくは国内・海外を問わず、自然の中を歩くことが多いので、行く先々で生育している植物にまず目がいきます。どんなものがあるかという興味とともに、食べられるか否かをすぐ考えるのです。それが、子どものころに身についたものであることは明らかですが、もしかしたら採集生活をしていた太古の時代の先祖のDNAを、濃密に受けついでいるのかもしれません。 いま考えれば、ほんとうにいい環境に育ったものです。畑でなくても、そこらじゅうに食べられるものがたくさんありました。木の実だけでなく、木の根、草の葉、草の根と、自然の恵みはバラエティに富んでいます。これを知っているのと知らないのとでは、大ちがいではないでしょうか。
比較的取りやすかったのはイヌマキの実です。庭木や生け垣にされるとてもポピュラーな木で、いたるところにありました。ふだんは単にマキと呼んでいました。中学校の校庭にも並木のように植えてあり、9月ごろになると実が熟します。実といってもほんとうの実(食べられません)の根元につく花托という部分らしいのですが、ブドウのような赤黒い色になり、食感はまるでゼリー。味は干したプルーンほど甘くはないものの、ちょっとそれに似た感じで、松ヤニのような風味もあります。 小学5年生のころにその味を知ったのはアオギリの実です。学校のサツマイモ畑で収穫がいったん終わったあと、友達と3人ほどで校庭の掃除の時間に畑を漁ってみたら、取り残しが結構あったので、それをゴミ焼き場で焼いていると、ほかのクラスの連中がこれと交換してくれないかと持ってきたのが、ぞうきんバケツに入れて煎ったアオギリの実だったのです。試食させてもらうと、大豆を煎ったのとそっくりでした。商談は成立、ぼくたちは焼き芋とアオギリの両方を食べることができました。 川の堤に行くと、春先にはツバナ(茅花)がありました。チガヤ(茅)という植物の花穂の部分です。完全に開いてしまう前の若い穂には甘味があり、それを味わうのです。芝の一種と思われる植物の根はそれよりも甘く、甘根と呼んでいました。ムラサキカタバミの茎は、酸っぱいものが欲しいときにかみました。カタバミは漢字で書くと「酢漿草」と書きます。蓚酸(しゅうさん)を含んでいるのだそうです。もちろんずっとあとで知りましたが、食べられるものを教えてくれたのは年長のガキ大将で、ぼくもまた下の世代にそれを伝えました。 最後にとっておきの思い出を。ぼくたちが「大人の味」と思っていたもの、それは肉桂です。京都銘菓の八つ橋に使われていたし、駄菓子屋で束にして売っていたり、ニッケ玉やニッケ水もありましたが、買わなくても手に入ったのです。ただし、当時でもどこにでもあるわけではありません。それを見つけてくるやつがいるんです。それなりのりっぱなお屋敷の庭でした。幸い、垣根から近かったので、上半身を少しだけ庭に入れて、移植ごてで根元をほじくり、直径1センチに満たない細い根を少しだけ、ほんの少しだけ失敬します。あとは元通りにしますから、気づかれる心配はありません。また、むやみに掘ると、木を傷めますから、限度をちゃんとわきまえていました。しかも、この情報はほんの数人の間にしか伝わっていませんでした。ほかでも同様のことが行われていたのかもしれませんが、仲間内での情報の拡散防止はいわば不文律のようなものでした。 |